10月9日(水)4限目に、令和6年度生徒会総会が行われました。新役員が任命され、新旧役員が交代しました。前会長から、今までの活動を支えてくれたことに対する感謝や新役員への期待と励ましの言葉が述べられました。そして、前生徒会役員3年生から感謝の気持ちを込めたプレゼントとして、1年間の活動を写し取ったスライド映像が流されました。また、心がこもったソーラン節の披露もありました。その後、校長から新役員に任命書が手渡され、最後に、新生徒会長による、前役員の活動に対する感謝の言葉、これからは自分たちが自覚と責任を持って活動していきたいという決意表明と、全校生への協力の呼びかけがなされ、生徒会総会は、良い雰囲気で締めくくられました。

(文責:高校教員)

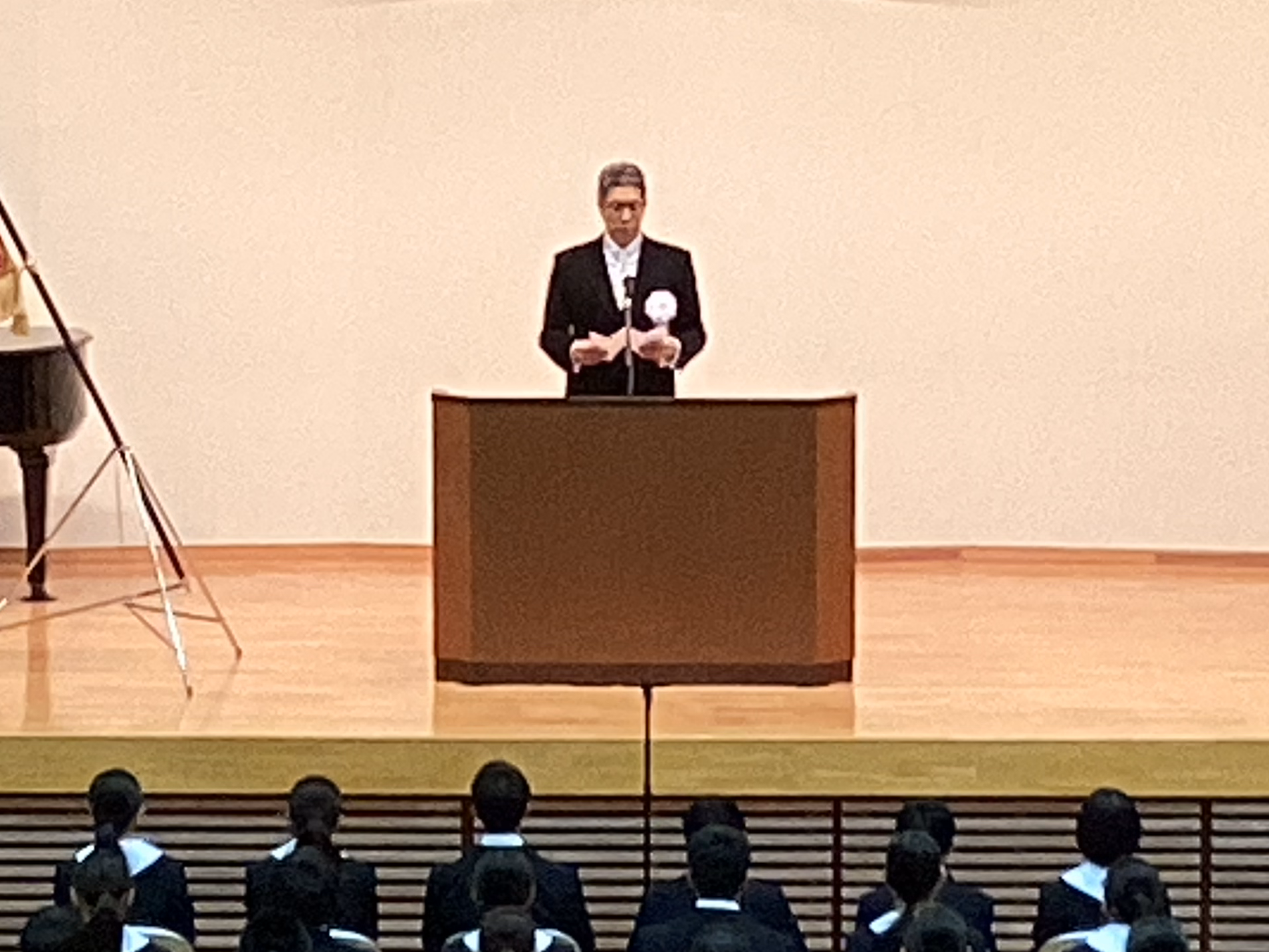
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
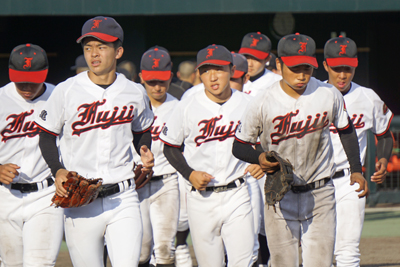
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)



































